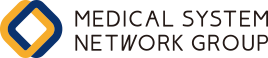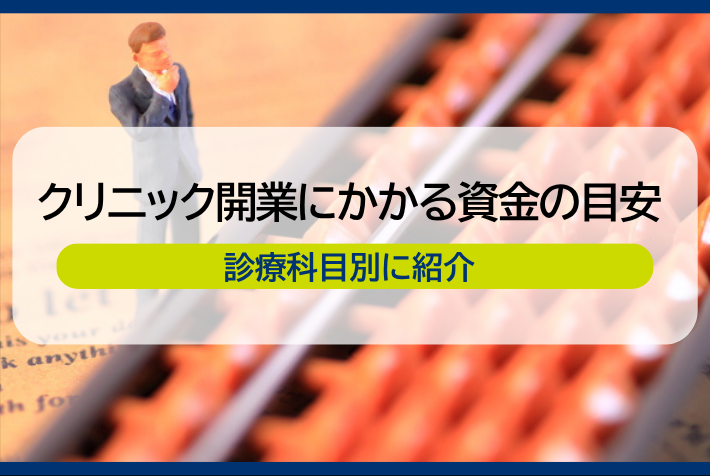クリニックの開業は、多くの医師にとって大きな挑戦です。中でも「開業資金」は最初にぶつかる大きな壁。
いくら必要なのか?自己資金はどれくらいあればいいのか?資金調達はどうすればいいのか?
こうした疑問に直面する方も多いはずです。
本記事では、診療科目ごとの開業費用の目安や、初期費用と運転資金の内訳、資金調達の選択肢まで開業資金にまつわる情報を紹介します。
【診療科目別】クリニック開業の資金の目安
クリニック開業の費用感をつかむうえで、「自分の専門領域ではどのくらい必要なのか」を知るのはとても重要です。同じ開業でも、内科と整形外科、皮膚科と眼科では必要な設備も患者層も異なるためです。
ここでは、主な診療科目ごとに開業資金の「目安」を一覧でまとめました。
| 診療科目 | 開業資金の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 内科 | 約5,000万円~8,000万円 | 消化器・循環器など専門領域では検査数が多いため上振れ |
| 小児科 | 約4,000万円~6,000万円 | キッズスペース・家族同伴・駐車場などを含めた設備設計が必要 |
| 皮膚科 | 約2,000万円~1億円 | レーザー・美容系機器を加えると上振れ |
| 整形外科 | 約5,000万円~1億円 | リハビリ設備・MRIなど高度検査機器を入れると上振れ |
| 耳鼻咽喉科 | 約4,000万円~8,000万円 | 内視鏡・聴力検査室・防音室など設備が増えると上振れ |
| 精神科・心療内科 | 約1,500万円~3,000万円 | 高度医療機器は不要なことが多く、設備費・人件費を抑えられる |
| 産科・婦人科 | 約5,000万円~6,000万円 | 分娩や不妊治療の対応を含めるとさらに増加 |
| 脳神経外科 | 約6,000万円~2億円 | CT・MRI・手術設備など導入するかによって大幅に変動 |
| 眼科 | 約1億~2億円 | 高額医療機器、手術設備など導入するかによって大幅に変動 |
※上記はあくまでも目安です。立地・規模・設備内容・物件形態によって大きく変動します。
開業資金の内訳
開業資金は、大きく「初期費用」と「運転資金」の2つに分けて考える必要があります。
初期費用(イニシャルコスト)
開業までに必要となる「モノ」や「手続き」にかかる費用です。特に医療機器費と内装費は、診療科やこだわりによって大きく変動するポイントです。
【初期費用の例】
・物件取得費(敷金、礼金、保証金、仲介手数料、前家賃など)
・内装や設計費(待合室、診察室、処置室、スタッフルーム等の設計・施工費)
・医療機器費(電子カルテ、レセコン、X線、超音波、診察台、滅菌器など)
・什器や備品費(PC、電話、FAX、待合室の椅子、デスク、ロッカーなど)
・広告宣伝費(HP制作、ロゴ、看板設置、開業告知のチラシ・Web広告費)
・諸経費(法人設立費用、医師会入会金、申請費用など)
運転資金(ランニングコスト)
開業後、クリニックの経営が軌道に乗るまでの間、経営を維持していくための「つなぎ資金」です。
なぜ運転資金が必要なのかと言うと、保険診療がメインの場合、診療報酬(売上)が実際に入金されるのは、診療月の約2~3ヶ月後。
つまり、開業後2~3ヶ月は、まとまった売上入金がない状態で、スタッフの給与や家賃を払い続けなければなりません。
【運転資金の例】
・人件費(看護師、受付、事務スタッフの給与、社会保険料)
・家賃
・医薬品や消耗品費
・水道光熱費
・リース料(医療機器をリースした場合)
・広告宣伝費(継続している場合)
開業資金が変動するポイントとは?
クリニックの開業資金に幅があるのは、先生がどのようなクリニックを目指すかによって、必要なコストが異なるためです。特に以下の5つのポイントは、資金計画全体に大きな影響を与えます。
1. 立地(都心/郊外)
開業する「場所」は、物件の費用と開業後の集患に関わるポイントです。当然ながら、都心の一等地やターミナル駅直結の医療モールは認知度が高く集患しやすい反面、賃料や保証金が高い傾向にあります。
逆に、郊外の住宅街であれば物件コストは抑えられますが、認知度を高めるための広告戦略や、患者さん用の駐車場確保といった別のコストが発生する可能性があります。
2. 物件(新築/テナント・スケルトン/居抜き)
立地と並んで初期費用に大きく影響するのが、物件の「形態」と「状態」です。土地を購入してクリニックを「戸建て新築」する場合であれば、億単位の投資になる可能性もあるでしょう。
多くの場合、「テナント入居」が現実的な選択肢となりますが、ここでも「スケルトン」か「居抜き」かで差が出ます。
「スケルトン」は内装が何もない状態から作るため設計の自由度が高いですが、工事費は高額。「居抜き」は、内装や設備(X線室の防護壁など)を流用できれば初期費用を抑えられます。
3. 診療科目(必要な医療機器)
専門とする「診療科目」によって必要な医療機器が異なることも、資金に差がでる要因です。高額な検査機器や診断機器を必要としない診療科目は初期費用を抑えやすいです。逆に、大型の機器や専門的な検査機器が必要な診療科目は、機器代だけで大きな差が出ます。
■ 費用が比較的抑えやすい科目
心療内科、精神科(高額な医療機器が少なく、内装や防音設備が費用の中心)
■ 費用が高額になりやすい科目
整形外科(X線、リハビリ機器一式)、眼科(各種検査機器)、消化器内科(内視鏡システム)
■ 導入機器で変動する科目
一般内科(X線、エコー、心電図の基本セットに加え、CTまで導入すると費用は大きく跳ね上がる)
4. 医療機器の調達方法(新品/中古/リース)
必要な医療機器が決まっても、それを「どう調達するか」にも資金に影響します。
すべて新品で揃えるのは安心感やメーカー保証の面で理想的ですが、その分高額になります。中古であれば初期費用は抑えられますが、故障リスクや保証の有無、信頼できる業者の選定が重要。
また、初期の自己資金を温存し、運転資金に回したい場合に検討できるのが「リース」です。初期費用(購入費)は発生しませんが、月々のリース料がかかります。
5. 内装・設計のこだわり
クリニックの「顔」となる内装や設計も、費用を変動させるポイントです。患者さんに快適に過ごしてもらうための清潔感や機能性は必須ですが、デザイン性や高級感を追求すれば、その分、設計費や工事費は上がっていきます。
スロープや多目的トイレといったバリアフリー設計や、近年のニーズに合わせた感染対策(高性能な換気システム、隔離室の設置)なども、こだわればこだわるほど費用が上がります。
クリニック開業資金を調達するには?
クリニック開業には、数千万円単位の資金が必要です。すべてを自己資金でまかなえるケースは稀であり、多くの医師が公的機関や金融機関からの融資を活用して開業資金を調達しています。
ここでは、開業資金の調達先を紹介します。
日本政策金融公庫(JFC)
個人開業医の融資先として最もよく使われているのが日本政策金融公庫(公庫)です。政府系金融機関のため、比較的低金利で長期返済が可能なのが特徴。医療業界に特化した融資制度があり、開業予定者でも実績なしで借りられるというメリットがあります。
独立行政法人福祉医療機構(WAM)
その名の通り、医療や福祉分野の施設整備を専門に支援している独立行政法人です。最大の魅力は、長期(例:20年超)かつ低金利で融資を受けられる点です。ただし、医療・福祉専門であるため、融資対象となる事業や設備の要件が定められており、審査が民間の銀行より厳しい傾向にあります。
民間の金融機関(銀行・信用金庫など)
メガバンク、地方銀行、信用金庫などの一般的な金融機関です。多くの銀行が医師向けの「ドクターローン」や「クリニック開業ローン」といった専用パッケージを用意しています。
金利や融資額は金融機関によって様々ですが、今後のメインバンクとして長期的な取引(スタッフの給与振込や将来の設備投資など)を視野に入れた交渉ができます。
補助金や助成金の活用
国や自治体から交付される医療施設向けの補助金・助成金制度を利用できる場合もあります。
ただし、すべてのクリニックが対象になるわけではなく、「地域医療を支える拠点」など明確な要件を満たす必要があります。
なお、補助金は「後払い(実績報告型)」が多く、事前申請が必要です。開業エリアの自治体サイトのほか、医療コンサルタントにも相談できます。
リース会社
医療機器や内装設備など、高額な初期投資が必要な項目をリースでまかなうことで、初期費用を抑えるのも一つの選択肢です。融資とは違って「借金ではない」という位置づけなので、資金繰りを安定させやすいメリットもあります。
開業にあたって「自己資金」はどの程度必要なのか?
ここまで開業資金全体の話をしてきましたが、資金のうち「自己資金」はどの程度必要なのでしょうか?
一つの目安としては「開業資金の2割」程度
開業資金のうち「どれくらいを自己資金として用意すべきか?」という疑問に対しては、「開業資金総額の約2割程度」が一つの目安とされています。
例えば、開業資金が6,000万円かかる場合、自己資金として1,200万円ほど準備できていると理想的と言えるでしょう。もちろん診療科目や物件によって金額は前後しますが、貯蓄があることで資金調達の負担を減らしやすくなります。
自己資金を用意するメリット
自己資金を用意しておくことで、次のようなメリットがあります。
■ 金融機関の融資審査で信頼を得やすい(資金を持っている=経営の見通しが立っていると評価される)
■ 開業後3〜6ヶ月分の運転資金(家賃・人件費など)を事前に確保できる
■ 内装費や広告費など、想定外の追加費用が発生した場合にも柔軟に対応できる
つまり、「返済に追われる不安」を減らしながら、余裕をもって開業準備を進めることができるのです。
自己資金がないと開業できない?
自己資金が開業資金の2割に満たないからといって、開業自体ができないわけではありません。最近は、金利の低い融資制度や医療機器のリースなども活用しやすくなっており、自己資金を抑えて開業する方法も広がっています。
ただし、自己資金が少ない場合は、次のような視点で綿密な事業計画書を準備しておくことが大切です。
■ 医療機器・内装費など、開業費用の内訳を明確に算出
■ 月々の返済額と固定経費(家賃・人件費など)を無理なく支払える設計か
■ 診療報酬の伸び・来院数など、収益の見通しが現実的かどうか
「資金計画に自信がない」「融資に通るか不安」という場合は、専門家である「開業コンサルタント」に相談するのもおすすめです。融資書類の準備から金融機関との交渉、返済シミュレーションまで一貫したサポートを受けられます。
クリニックの開業なら『メディカルシステムネットワーク』にお任せください
メディカルシステムネットワークには、全国展開している調剤薬局事業のネットワークを活かして、医師と共に「地域医療」を創り上げるというビジョンがあります。
そのため、クリニックの開業という夢を無料のコンサルティングでサポートしております。
★Point 01 コンサルタント料金は「無料」
開業のコンサルタント費用はかかりません。
「地域に根差した医療を先生と一緒につくる」というビジョンのもと、調剤薬局の併設も視野に入れながら支援いたします。
★Point 02 開業準備のすべてを任せられる「ワンストップ体制」
開業には資金計画・設計・広告・求人など多くの準備が必要です。
担当者がパートナーとなり、専門業者と連携しながら事業計画から採用までトータルで支援いたします。
★Point 03 開業後も続く「アフターフォロー」
開業した後もサポートは続きます。
健康セミナーや講演会の開催支援など集患・増患につながる企画をご提案。医業承継を考えるタイミングでの準備もサポートします。
★Point 04 集患に有利な「メディカルモール」も守備範囲
複数の医療機関を同じ敷地に集めることで、患者さんは一度に複数の診療科を受診可能。
先生方にとっては施設共有によるコスト削減や集患効果で効率的な経営ができます。
★Point 05 「診療圏調査」を無料で実施
独自のデータベースを基に、診療圏のマーケティング調査を無料でご提供。調査だけのご相談も可能です。
開業準備から開設後の医院経営まで、調剤薬局事業で培ったノウハウを活かしてサポートいたします。まずはヒアリングにて、理想のクリニック像をお聞かせください。
まとめ
クリニック開業には数千万円規模の資金が必要になりますが、その金額は診療科目や立地、設備のこだわりによって大きく変動します。特に押さえておきたいポイントは以下の通りです。
■ 診療科目によって必要な医療機器や設備が異なり、開業資金の目安も変わる
■ 費用は「初期費用」と「運転資金」に分けて考える
■ 物件の形態(新築/テナント/居抜き)や内装へのこだわりも金額に影響する
■ 資金調達は日本政策金融公庫や民間金融機関、補助金など複数の手段がある
■ 一般的に「開業資金の2割程度」の自己資金があると理想的(少なくても開業は可能)
不安や疑問がある場合は、クリニックの開業に詳しいコンサルタントに相談することも一つの選択肢です。
メディカルシステムネットワークでは、無料コンサルタントで開業を目指す先生をサポートしています。お気軽にご相談ください。